2025年01月10日【ピックアップ】
世界初のiPS細胞臨床応用への挑戦
iPS細胞はES細胞の課題を解決すると期待されていた
2007年11月に、山中伸弥先生(京都大学)らは、ヒトの皮膚細胞からiPS細胞(人工多能性幹細胞)を作り出すことに成功し、科学雑誌『Cell』に発表しました。ヒトiPS細胞は、ヒト胚性幹細胞(ES細胞)に匹敵する能力をもつ幹細胞です。ヒトES細胞は、受精卵を原料とするため、倫理的問題を抱えていました。また、他人の細胞であるため、再生医療等製品とするためには、免疫拒絶反応の課題もありました。iPS細胞は、自分の細胞を原料とするため、倫理的問題や、免疫拒絶反応の課題を解決できることが期待されました。
その頃、髙橋政代先生(理化学研究所)らは、ヒトES細胞を原料として、網膜色素上皮細胞に分化させ、加齢黄斑変性の患者さんに移植する治療法を開発していました。当時の日本では、ES細胞を移植医療に使う倫理的ハードルが高く、開発は難航していました。ヒトiPS細胞の発明により、一気にこれらの課題が解決し、開発が加速する機運が高まりました。
挑戦は2009年に始まった
ヒトiPS細胞が発表されてから2年後の2009年秋、当社は、髙橋先生から、国の委託業務である『iPS細胞由来網膜色素上皮細胞移植による加齢黄斑変性治療の開発』への参画を要請されました。このプロジェクトの目的は、iPS細胞由来網膜色素上皮細胞移植による加齢黄斑変性治療について、医師主導の臨床研究を開始することでした。日本初の再生医療等製品の製造販売承認を取得した実績に基づき、当社が有する細胞製品関連通知・規制の解釈・運用、及びGMP基準の細胞製品を製造可能な細胞培養加工施設(CPC)の管理運用等に関するノウハウを生かし、世界初のiPS細胞由来細胞治療の実現化を支援する重大な役割をいただいたのです。
安全性の確認や手順書作成をサポート
細胞製品の製造過程では、細胞を培養するために、様々な生物(ヒトや動物)由来原料が使われます。これらの原料は国内外の試薬会社から購入し、ヒトへの移植時の安全性を確認する必要があります。機密情報の観点から、情報開示ができないという会社が多い状況において、安全性を確認することは大変な作業でした。時には、山中先生のご協力も得ながら、試薬会社と当社が交渉し、安全性を担保できる環境を整えました。
CPCの運用方法や、原料となるヒト組織および移植する製品を輸送する専用容器の開発についても、当社はこれまでの再生医療等製品の製造販売のノウハウを活かし、数多くの標準作業手順書(SOP)を作成するとともに実績に基づく助言もしました。
わずか7年で世界初の臨床応用が実現
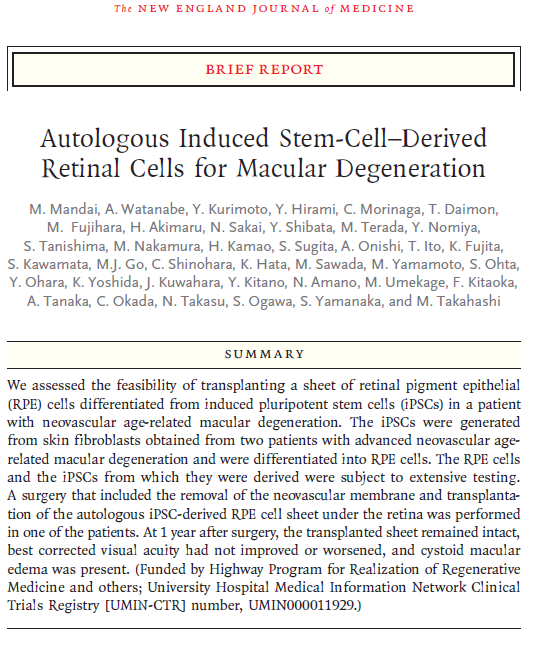
こうして、2007年11月のヒトiPS細胞の報告から、わずか7年後の2014年9月12日、髙橋先生のグループは、世界初の患者さん自身のiPS細胞由来網膜色素上皮細胞移植による加齢黄斑変性治療を行いました。髙橋先生からは、J-TECの果たした役割に多大な感謝をいただき、世界初の臨床研究を発表した、科学雑誌New England Journal of Medicineの著者に、当社の畠と篠原を加えていただきました。
iPS細胞由来の製品化実現に向けて
当社は、世界初のiPS細胞をつかった再生医療の実現に関わることができました。一方で、世界初のヒトへの移植がなされた2014年から10年が経過した今も、未だに承認されたiPS細胞由来の再生医療等製品は、世界中で存在しません。今後は、その実現化にも深くかかわっていきたいと考えています。


